
「筋トレしてるのに体重が増えてる…?」と不安を感じていませんか? せっかく頑張ってトレーニングしているのに、体重が増加してしまうとモチベーションも下がってしまいますよね。実は、筋トレ初期に体重が増えるのはよくあることで、必ずしも悪いことではありません。このページでは、筋トレで体重が増加するメカニズム、その意外な原因、そして効果的な対策を分かりやすく解説します。筋肉が増えつつ体脂肪を減らすための適切なカロリー摂取量、PFCバランス、トレーニング方法、そしてよくある誤解まで、具体的な例を交えながら徹底的に解説していきます。この記事を読めば、体重増加の本当の原因を理解し、理想の体型に近づくための正しい知識と具体的な方法を身につけることができます。もう体重計の数値に一喜一憂する必要はありません。正しい知識を身につけて、自信を持ってトレーニングに取り組み、理想の体型を手に入れましょう。
1. 筋トレで太るメカニズム

筋トレを始めたのに、体重が増えてしまい悩んでいる方はいませんか?実は、筋トレ直後に体重が増加するのはよくあることで、必ずしも体脂肪が増えているとは限りません。ここでは、筋トレによって体重が増加するメカニズムを解説します。
1.1 筋肉の増加と体重増加の関係
筋肉は脂肪よりも密度が高い組織です。つまり、同じ体積であれば筋肉の方が脂肪よりも重くなります。筋トレによって筋肉量が増加すると、たとえ体脂肪が減っていたとしても、体重計の数値は増加することがあります。そのため、体重計の数字だけで一喜一憂するのではなく、体組成計などを用いて体脂肪率や筋肉量の変化を確認することが重要です。
1.2 水分貯留の影響
筋トレを行うと、筋肉に微細な損傷が生じます。これを修復するために、体は水分を筋肉に蓄えようとします。この水分貯留も体重増加の一因となります。また、筋トレ中は筋肉に多くの血液が送られるため、一時的に筋肉が膨張し、体重が増加することもあります。この水分貯留による体重増加は一時的なもので、数日後には元に戻ることが一般的です。
さらに、筋トレによってグリコーゲンが筋肉に蓄積されます。グリコーゲンはエネルギー源として利用される物質で、水分を保持する性質があります。そのため、グリコーゲンの増加も体重増加に影響を与えます。特に筋トレを始めたばかりの頃は、グリコーゲンの蓄積量が増えやすい傾向にあるため、体重増加が目立つことがあります。
| 要因 | 詳細 |
| 筋肉の増加 | 筋肉は脂肪より密度が高いため、体積あたりの重量が大きい。 |
| 水分貯留 | 筋肉の修復、血液供給の増加、グリコーゲンの蓄積により水分が貯留される。 |
| グリコーゲン | エネルギー源であるグリコーゲンは水分を保持する性質を持つため、その増加は体重増加に繋がる。 |
これらの要因から、筋トレ初期は体重が増加しやすい傾向にあります。しかし、これは体脂肪が増えているわけではなく、筋肉の成長や水分貯留による一時的な現象です。継続して筋トレを行い、適切な食事管理を行うことで、体脂肪を減らし、理想的な体型に近づくことができます。
2. 筋トレしてるのに太る意外な原因

筋トレを頑張っているのに、体重が増えてしまう。そんな経験はありませんか?実は、筋トレと体重増加には複雑な関係があり、いくつかの意外な原因が潜んでいるかもしれません。ここでは、その原因を詳しく解説し、効果的な対策をご紹介します。
2.1 過剰なカロリー摂取
筋トレで筋肉を大きくするためには、タンパク質はもちろんのこと、エネルギー源となる炭水化物や脂質も必要です。しかし、必要以上に摂取してしまうと、脂肪として蓄積され、体重増加につながります。特に、トレーニング後に食欲が増し、ついつい食べ過ぎてしまう傾向がある方は要注意です。
2.1.1 タンパク質の過剰摂取
筋肉の成長にはタンパク質が不可欠ですが、過剰に摂取しても筋肉の成長は促進されません。余剰なタンパク質は体内で脂肪に変換され、体重増加の原因となります。1日に必要なタンパク質量は、体重1kgあたり1.6~2g程度と言われています。プロテインなどを摂取する際は、自分の体重や活動量に合わせた適切な量を摂取するようにしましょう。
2.1.2 炭水化物・脂質の過剰摂取
炭水化物と脂質は、トレーニングに必要なエネルギー源です。しかし、消費カロリーを上回る量の炭水化物や脂質を摂取すると、体脂肪として蓄積されます。特に、糖質の多い清涼飲料水や脂質の多い揚げ物、お菓子などは注意が必要です。バランスの良い食事を心がけ、炭水化物と脂質の摂取量をコントロールしましょう。
2.2 トレーニング後のドカ食い
トレーニング後は、食欲が増し、つい食べ過ぎてしまうことがあります。「せっかく筋トレしたから」と、高カロリーな食事を摂ってしまうのは逆効果です。トレーニング後の食事は、筋肉の修復と成長を促すための栄養補給と捉え、適切な量と質の食事を心がけましょう。
2.3 不適切なトレーニング方法
トレーニング方法が適切でない場合も、体重増加につながることがあります。例えば、筋トレの強度が低すぎたり、特定の筋肉ばかり鍛えていたりすると、効果的に筋肉を Hypertrophyさせることができません。
※Hypertrophy(ハイパートロフィー)とは、細胞のサイズが大きくなること、つまり「肥大化」や「発達」を意味します。
2.3.1 筋トレの強度不足
軽い負荷の筋トレでは、筋肉への刺激が不足し、効果的な筋肥大が期待できません。適切な負荷を設定し、筋肉に十分な刺激を与えることが重要です。セットごとに限界まで追い込むようなトレーニングを心がけましょう。また、徐々に負荷を上げていくことも大切です。
2.3.2 筋トレの種類の偏り
特定の部位ばかり鍛えていると、全身の筋肉バランスが崩れ、効果的な筋肥大が阻害される可能性があります。全身の筋肉をバランスよく鍛えることで、基礎代謝が向上し、効率的に脂肪を燃焼することができます。大きな筋肉群である、脚、背中、胸を鍛えることを意識しましょう。スクワット、デッドリフト、ベンチプレスなどの複合関節運動を取り入れるのが効果的です。
2.4 睡眠不足
睡眠不足は、成長ホルモンの分泌を抑制し、筋肉の成長を妨げます。また、食欲を増進させるホルモンの分泌を促進するため、過食につながる可能性も高まります。1日7~8時間の質の高い睡眠を確保するように心がけましょう。
2.5 ストレス
ストレスは、コルチゾールというホルモンの分泌を促進します。コルチゾールは、筋肉の分解を促進し、脂肪の蓄積を促す作用があります。ストレスを溜め込まないよう、適度な運動や趣味、リラックスできる時間を設けることが大切です。
2.6 ホルモンバランスの乱れ
甲状腺ホルモンや成長ホルモンなどのホルモンバランスの乱れは、代謝を低下させ、体重増加につながることがあります。バランスの取れた食事、規則正しい生活、十分な睡眠を心がけ、ホルモンバランスを整えるようにしましょう。気になる場合は、医療機関に相談することも検討しましょう。
3. 筋トレの効果を高める食事方法
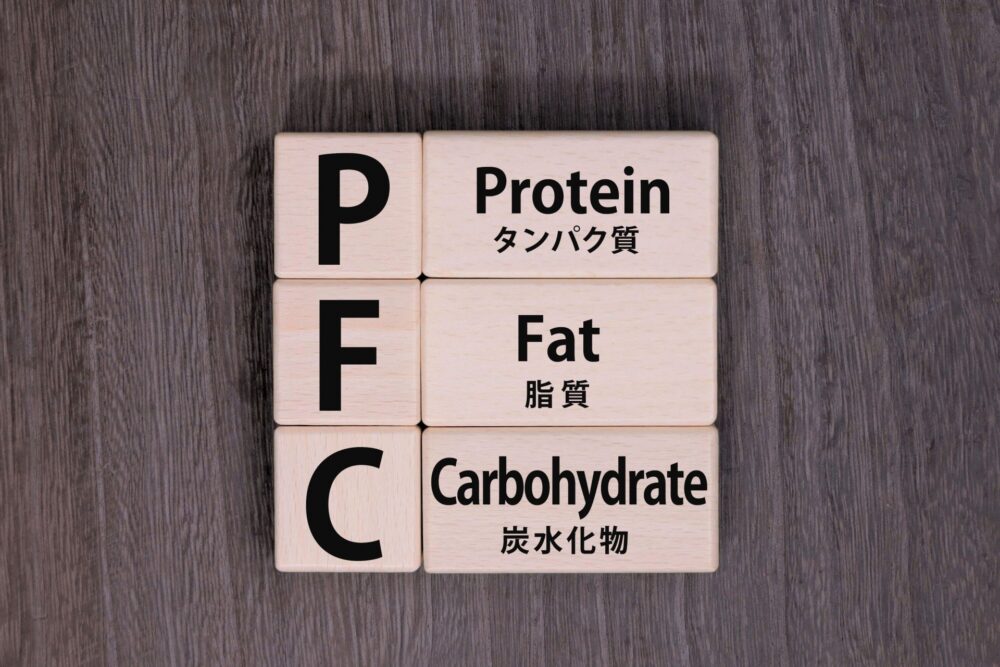
筋トレで効果を出すためには、トレーニングだけでなく食事も非常に重要です。適切な栄養摂取は、筋肉の成長を促進し、体脂肪の減少をサポートします。この章では、筋トレの効果を高めるための食事方法について詳しく解説します。
3.1 適切なカロリー摂取量を知る
まず大切なのは、自身の基礎代謝量と活動代謝量を把握し、それに基づいて適切なカロリー摂取量を計算することです。摂取カロリーが少なすぎると筋肉の成長が阻害され、多すぎると体脂肪が増加してしまいます。オンラインのカロリー計算ツールなどを活用して、自分の消費カロリーを把握し、目標に合わせた摂取カロリーを設定しましょう。
3.2 PFCバランスを意識した食事
PFCバランスとは、三大栄養素であるタンパク質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)の摂取比率のことです。筋トレの効果を高めるためには、このバランスを適切に調整することが重要です。
3.2.1 タンパク質の摂取量とタイミング
タンパク質は筋肉の構成要素となるため、積極的に摂取する必要があります。体重1kgあたり1.6~2gを目安に、肉、魚、卵、大豆製品、乳製品など良質なタンパク質源から摂取しましょう。また、トレーニング後や就寝前など、筋肉の合成が活発になるタイミングで摂取することも効果的です。
3.2.2 炭水化物の種類と摂取タイミング
炭水化物はトレーニングのエネルギー源となるため、不足するとパフォーマンスが低下します。白米、パン、麺類などの精製された炭水化物よりも、玄米、全粒粉パン、オートミールなどの未精製炭水化物を選ぶようにしましょう。トレーニング前後に摂取することで、エネルギー補給と筋肉の回復を促進できます。
3.2.3 脂質の種類と摂取量
脂質はホルモンの生成や細胞膜の構成に関わる重要な栄養素です。魚、ナッツ、アボカドなどに含まれる良質な脂質を摂取するように心がけましょう。過剰摂取は体脂肪増加につながるため、摂取量には注意が必要です。
| 栄養素 | 役割 | 摂取量の目安 | 摂取タイミング | おすすめの食品 |
| タンパク質 | 筋肉の構成要素 | 体重1kgあたり1.6~2g | トレーニング後、就寝前など | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| 炭水化物 | トレーニングのエネルギー源 | 総摂取カロリーの50~60% | トレーニング前後 | 玄米、全粒粉パン、オートミール |
| 脂質 | ホルモンの生成、細胞膜の構成 | 総摂取カロリーの20~30% | 毎食 | 魚、ナッツ、アボカド |
3.3 サプリメントの活用方法
プロテイン、クレアチン、BCAAなど、筋トレの効果を高めるためのサプリメントは様々な種類があります。これらのサプリメントは、食事からの栄養摂取が不足している場合に補助的に活用するのが効果的です。自身のトレーニング目標や食生活に合わせて、適切なサプリメントを選びましょう。過剰摂取は健康に悪影響を与える可能性があるため、用法用量を守ることが大切です。
3.4 食事の記録と管理
食事の内容やカロリー、PFCバランスを記録することで、自身の食生活を客観的に把握し、改善点を見つけることができます。食事記録アプリなどを活用して、継続的に食事管理を行いましょう。記録することで、食生活の改善点に気づき、より効果的な食事プランを立てることができます。
4. 筋トレの効果を高めるトレーニング方法

せっかく筋トレをしているのに、思うように効果が出ないと悩んでいませんか?正しいトレーニング方法を行うことで、効率的に筋肉を鍛え、理想の体型に近づくことができます。ここでは、筋トレの効果を最大限に引き出すためのトレーニング方法を詳しく解説します。
4.1 適切なトレーニング強度を設定する
トレーニング強度が低すぎると筋肉への刺激が不足し、効果が得られにくくなります。逆に、高すぎると怪我のリスクが高まり、トレーニングを継続することが難しくなります。自分の体力レベルに合った適切な強度を設定することが重要です。
トレーニング強度を設定する際の目安としては、1セットの動作を限界まで行う回数(反復回数)で調整する方法があります。8回~12回程度で限界がくる重量を選ぶと、筋肥大に効果的と言われています。また、インターバル(セット間の休憩時間)も重要です。筋肥大を目的とする場合は、1分~3分程度のインターバルを取り、筋肉を十分に回復させましょう。
4.2 筋トレメニューのバリエーションを増やす
同じトレーニングメニューを繰り返していると、体がその刺激に慣れてしまい、効果が停滞する可能性があります。様々な種類のトレーニングを取り入れることで、全身の筋肉をバランス良く鍛え、効果的に筋肥大を促進することができます。
例えば、スクワット、ベンチプレス、デッドリフトなどのBIG3と呼ばれる基本的なトレーニングに加えて、ダンベルやバーベルを使った様々な種目を組み合わせることで、より効果的なトレーニングを行うことができます。また、自重トレーニングも有効です。腕立て伏せや腹筋運動など、場所を選ばずに手軽に行えるため、トレーニングのバリエーションを広げるのに役立ちます。
4.3 トレーニングの頻度と休息
トレーニングの頻度も重要な要素です。毎日トレーニングを行うよりも、適切な休息を挟むことで、筋肉の回復と成長を促すことができます。一般的には、週2~3回のトレーニングが推奨されています。部位ごとにトレーニング日を分ける分割法も効果的です。
| トレーニング頻度 | メリット | デメリット |
| 週2~3回 | 休息日を確保しやすく、筋肉の回復を促せる。 | トレーニングに慣れていない場合は、効果を実感するまでに時間がかかる場合がある。 |
| 週4~5回(分割法) | 集中的に各部位を鍛えることができる。 | トレーニングのスケジュール管理が複雑になる場合がある。 |
4.4 正しいフォームでトレーニングする
正しいフォームでトレーニングを行うことは、効果を高めるだけでなく、怪我の予防にも繋がります。誤ったフォームでトレーニングを行うと、狙った筋肉に刺激が伝わりにくく、効果が半減してしまうだけでなく、関節や靭帯を痛めてしまう可能性があります。
トレーニングを始める前に、正しいフォームを動画や書籍で確認したり、トレーナーに指導を受けるのがおすすめです。鏡を見ながら自分のフォームをチェックすることも効果的です。また、重量を上げすぎるとフォームが崩れやすくなるため、無理のない重量で行うようにしましょう。
4.5 ウォーミングアップとクールダウン
トレーニング前にはウォーミングアップ、トレーニング後にはクールダウンを行うことで、怪我の予防や疲労回復に効果があります。ウォーミングアップは、軽い有酸素運動やストレッチなどで体を温め、筋肉の柔軟性を高めることを目的とします。クールダウンは、ストレッチなどで筋肉の緊張をほぐし、疲労物質の排出を促進します。
ウォーミングアップは5~10分程度、クールダウンも同様に5~10分程度行うのが目安です。これらの時間を確保することで、より安全で効果的なトレーニングを行うことができます。
5. 筋トレと体重管理のよくある誤解

筋トレを始めたばかりの方の中には、体重計の数値だけに注目して一喜一憂してしまう方が少なくありません。しかし、体重計の数値は、体組成の変化を正確に反映しているとは限りません。筋トレによって体が変化していく過程では、いくつかの誤解が生じやすいポイントがあります。それらを理解することで、トレーニングのモチベーションを維持し、効果的に目標達成へと近づけることができるでしょう。
5.1 体重計の数値にとらわれすぎない
筋トレを始めると、筋肉量が増加する一方で、体脂肪が減少することがあります。筋肉は脂肪よりも密度が高いため、同じ重さでも体積が小さくなります。そのため、体重計の数値に大きな変化が見られなくても、実際には体組成が改善されている可能性があります。体重計の数値だけに注目するのではなく、鏡で自分の体形を確認したり、衣服のサイズ感の変化に気を配ったりすることも大切です。
また、トレーニング直後は、筋肉に水分が貯留するため、一時的に体重が増加することがあります。これは、トレーニングによって筋肉がダメージを受け、修復される過程で起こる自然な現象です。一時的な体重増加に過剰に反応せず、長期的な変化に注目しましょう。
5.2 体脂肪率と筋肉量のバランス
健康的な体を作るためには、体重だけでなく、体脂肪率と筋肉量のバランスが重要です。体脂肪率が高すぎると、生活習慣病のリスクが高まることが知られています。一方、筋肉量が少ないと、基礎代謝が低下し、太りやすい体質になる可能性があります。筋トレによって筋肉量を増やし、体脂肪率を適切な範囲に保つことで、健康的な体を手に入れることができるでしょう。
理想的な体脂肪率は、年齢や性別によって異なります。一般的には、男性で15~20%、女性で20~25%程度が良いとされています。体脂肪率を測定するには、体組成計を利用するのが便利です。家庭用の体組成計でも、ある程度の精度で測定することができます。
| 項目 | 望ましい状態 | 注意点 |
| 体重 | 体組成の変化に合わせて評価 | 筋肉量の増加により一時的に増加する場合もある |
| 体脂肪率 | 男性:15~20%女性:20~25% | 体組成計を用いて定期的に測定 |
| 筋肉量 | 増加を目指す | 適切なトレーニングと栄養摂取が必要 |
これらのポイントを踏まえ、体重計の数値にとらわれすぎず、体脂肪率と筋肉量のバランスを意識しながら、トレーニングに取り組むことが大切です。焦らず、継続的に努力することで、理想の体に近づけるでしょう。
6. 筋トレの効果的な対策と成功事例

筋トレを頑張っているのに、思うように効果が出ない、むしろ体重が増えてしまう…。そんな悩みを抱えている方はいませんか?ここでは、筋トレの効果を最大限に引き出し、理想の体型に近づくための効果的な対策と、実際に成功した方の事例をご紹介します。
6.1 具体的な食事メニュー例
効果的な筋トレには、トレーニングだけでなく食事管理も不可欠です。ここでは、1週間の食事メニュー例を3パターンご紹介します。ポイントは、PFCバランスを意識し、それぞれの目的に合わせた栄養素を摂取することです。
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
| パターン1(増量期) | 朝食:ご飯、納豆、卵、味噌汁昼食:鶏胸肉のソテー、玄米、サラダ 夕食:鮭の塩焼き、ご飯、野菜炒め、味噌汁 | 朝食:プロテイン、バナナ、オートミール 昼食:牛丼、サラダ夕食:豚肉の生姜焼き、ご飯、味噌汁、ひじきの煮物 | 朝食:ご飯、目玉焼き、ウインナー、味噌汁 昼食:パスタ、ミートソース 夕食:焼き鳥、ご飯、サラダ、味噌汁 | 朝食:プロテイン、ヨーグルト、フルーツ 昼食:蕎麦、天ぷら夕食:ハンバーグ、ご飯、マカロニサラダ、味噌汁 | 朝食:ご飯、鮭フレーク、卵焼き、味噌汁昼食:カレーライス、サラダ 夕食:ステーキ、ご飯、ほうれん草のおひたし、味噌汁 | 朝食:パンケーキ、ベーコン、サラダ 昼食:ラーメン、餃子夕食:焼肉、ご飯、キムチ、わかめスープ | 朝食:フレンチトースト、サラダ昼食:寿司夕食:お好み焼き、焼きそば |
| パターン2(維持期) | 朝食:ヨーグルト、フルーツ、グラノーラ 昼食:鶏胸肉のサラダチキン、玄米、サラダ夕食:魚の煮付け、ご飯、野菜炒め、味噌汁 | 朝食:プロテイン、バナナ、オートミール 昼食:親子丼、サラダ夕食:豚肉の野菜炒め、ご飯、味噌汁、きんぴらごぼう | 朝食:全粒粉パン、スクランブルエッグ、サラダ 昼食:パスタ、ペペロンチーノ 夕食:鶏肉の照り焼き、ご飯、サラダ、味噌汁 | 朝食:プロテイン、ヨーグルト、フルーツ 昼食:蕎麦夕食:豆腐ハンバーグ、ご飯、グリーンサラダ、味噌汁 | 朝食:ご飯、ツナマヨ、卵焼き、味噌汁昼食:ハヤシライス、サラダ 夕食:鶏むね肉のソテー、ご飯、ほうれん草のおひたし、味噌汁 | 朝食:サンドイッチ 昼食:うどん 夕食:しゃぶしゃぶ、野菜 | 朝食:ワッフル、フルーツ 昼食:海鮮丼 夕食:手巻き寿司 |
| パターン3(減量期) | 朝食:ギリシャヨーグルト、フルーツ 昼食:鶏胸肉のサラダチキン、ブロッコリー、サラダ夕食:白身魚の蒸し焼き、きのこのソテー、味噌汁 | 朝食:プロテイン、バナナ 昼食:鶏肉の豆腐ハンバーグ、サラダ 夕食:豚肉の野菜炒め、きのこ汁、ひじきの煮物 | 朝食:全粒粉パン、ゆで卵、サラダ 昼食:きのこのパスタ夕食:鶏肉のハーブ焼き、サラダ、味噌汁 | 朝食:プロテイン、ヨーグルト 昼食:蕎麦夕食:きのこの和風ハンバーグ、グリーンサラダ、味噌汁 | 朝食:ご飯、ツナ、卵焼き、味噌汁 昼食:豆腐と野菜のカレー、サラダ 夕食:鶏むね肉のソテー、ほうれん草のおひたし、味噌汁 | 朝食:サラダチキンサンド 昼食:ざるそば 夕食:湯豆腐、野菜 | 朝食:オートミール、フルーツ 昼食:刺身定食 夕食:野菜炒め |
これらのメニューはあくまで一例です。自身の活動量や目標に合わせて、適宜調整しましょう。食事の記録をつけ、自分の体に最適な食事を見つけることが重要です。
6.2 具体的なトレーニングメニュー例
トレーニングメニューも、目的別に3パターンご紹介します。正しいフォームで、適切な負荷で行うことが大切です。また、週に2~3回の頻度で行い、筋肉を休ませることも重要です。
6.2.1 週2~3回の実施を推奨するトレーニングメニュー例
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
| パターン1(全身) | スクワット、ベンチプレス、デッドリフト、懸垂、腹筋 | 休息 | スクワット、ショルダープレス、ベントオーバーロウ、ディップス、プランク | 休息 | スクワット、ベンチプレス、デッドリフト、懸垂、腹筋 | 休息 | 休息 |
| パターン2(分割A) | 胸、肩、三頭筋 | 休息 | 背中、二頭筋 | 休息 | 脚、腹筋 | 休息 | 休息 |
| パターン3(分割B) | 脚、腹筋 | 休息 | 胸、肩、三頭筋 | 休息 | 背中、二頭筋 | 休息 | 休息 |
自身の体力レベルに合わせて、回数やセット数を調整しましょう。また、動画や専門家の指導を受けながら、正しいフォームを習得することも重要です。
7. まとめ
筋トレをしているのに体重が増加してしまう原因は、筋肉量の増加、水分貯留、過剰なカロリー摂取、不適切なトレーニング、睡眠不足、ストレス、ホルモンバランスの乱れなど、多岐にわたります。特に、タンパク質や炭水化物、脂質といった栄養素の過剰摂取は体重増加に大きく影響します。トレーニング後のドカ食いも要注意です。筋トレの効果を高めるためには、適切なカロリー摂取とPFCバランスを意識した食事管理、そして、適切な強度とバリエーションのあるトレーニングメニューの実施が不可欠です。体重計の数値だけに囚われず、体脂肪率と筋肉量のバランスを意識しましょう。本記事で紹介した食事メニュー例やトレーニングメニュー例、成功者の体験談を参考に、自分に合った方法を見つけて、理想の体型を目指してください。効果的な筋トレと適切な食事管理で、健康的なボディメイクを実現しましょう。
店舗情報
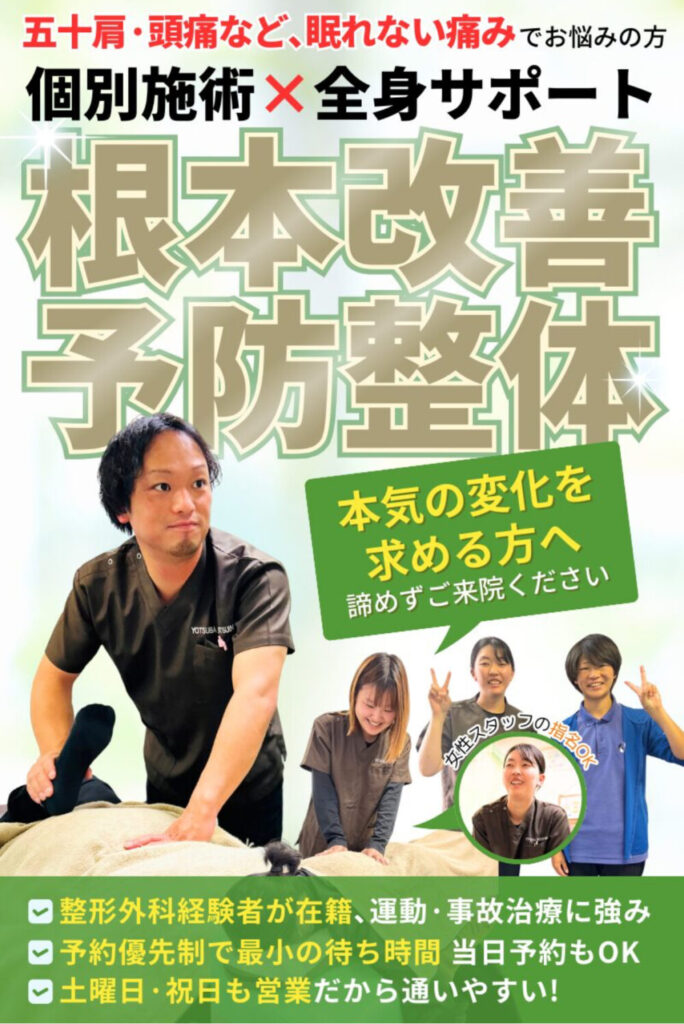
店舗名よつば整骨院/よつば整体院
代表髙橋 勇輝(たかはし ゆうき)
住所〒020-0851
岩手県盛岡市向中野7丁目1−36グレース向中野103
駐車場あり
地図を見る
営業時間9:00〜12:00/14:30〜19:30
火·金·土曜は18時まで通し営業
詳細はこちら
休診日日曜・祝日
アクセス盛岡南ICから2.5km
イオンモール盛岡南から1.3km
しゃぶしゃぶ温野菜 盛岡南店さん近く
TEL 019-681-2280
施術中はお電話に出られません。
留守番電話に「お名前」「お電話番号」をお残しください。
こちらから折り返しご連絡させていただきます。
営業時間
よつば整骨院/よつば整体院は 「 当日予約OK 完全予約制 」 です。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |
| 14:30〜19:30 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |
| 9:00〜18:00 | – | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | 休 | 休 |
9:00〜12:00/14:30〜19:30
火・金・土曜日は18:00まで通し営業となります



















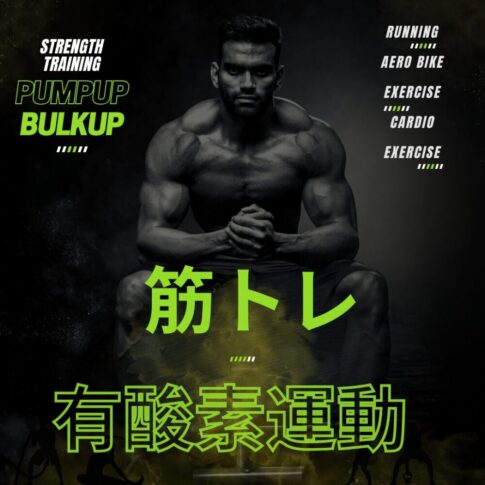


コメントを残す